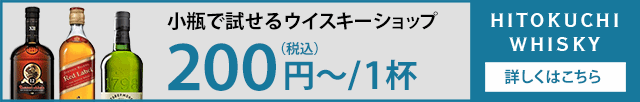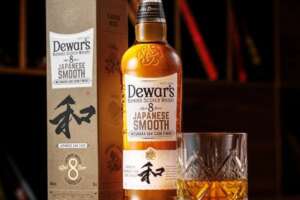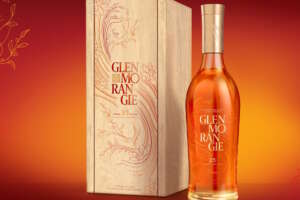JSLMAは、2021年2月に「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」を制定し、2024年4月から本格施行しています。
しかし、海外市場では基準に適合しない製品が「ジャパニーズウイスキー」として販売されている現状があり、消費者の混乱を招いています。
この状況を改善するため、組合は新たなロゴマークを制定しました。
このロゴは、ウイスキー樽の鏡板中央に「JW」を配置し、その周囲に「JAPANESE WHISKY」と「JSLMA」を組み合わせたデザインとなっています。
既に日本国内で商標登録の出願を行っており、今後、海外での手続きも進める予定です。
世界に広がる評価と、求められるルールづくり
ジャパニーズウイスキーは、その繊細な味わいと職人技により、世界中で高い評価を得ています。
2000年代以降の人気上昇とともに市場価値も急騰しましたが、一方で「ジャパニーズウイスキー」と称しながら、実態は輸入原酒やウイスキーとは呼べない混成酒である製品が出回り、消費者の混乱や信頼の損失を招く状況が問題視されてきました。
これまで日本の酒税法では「ジャパニーズウイスキー」の法的定義が存在せず、その曖昧さが悪用されてきた背景があります。
自主基準から始まった業界の動き
こうした状況を受けて、日本洋酒酒造組合(JSLMA)は2021年に「ジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」を制定し、3年の移行期間を経て2024年4月に本格施行しました。この基準は、ジャパニーズウイスキーの定義と品質基準を明確化するもので、消費者保護と業界の健全な成長を目指す重要な第一歩です。
新基準の主なポイント
JSLMAの新基準によれば、「ジャパニーズウイスキー」と名乗るには以下の要件を満たす必要があります。
主原料は麦芽。必要に応じて他の穀物を加えることも可。
水は日本国内で採水されたものを使用。
糖化、発酵、蒸留、瓶詰めはすべて日本国内で実施。
蒸留時のアルコール度数は95%未満。
700リットル以下の木製樽で3年以上熟成。
瓶詰め時のアルコール度数は40%以上。
着色はプレーンカラメル(無香料)のみ可。
そして今回、JSLMAは新たにロゴマークも制定しました。
ウイスキー樽の鏡板をモチーフに、「JW」や「JSLMA」の文字が配されたデザインで、消費者が基準を満たす製品を見分けやすくするための仕組みです。
さらに、基準に適合しない製品については、日本的な名前や地名、国旗、文化的イメージなどを使った誤認を招く表現を制限するガイドラインも定めています。
偽造品・誤表示への対策と期待される効果
近年では、「山崎」や「響」といった有名ブランドの空き瓶を利用した偽造品や、輸入原酒を日本でブレンドしただけの製品が「ジャパニーズウイスキー」として販売されるケースも確認されており、ブランドイメージや消費者信頼への影響が懸念されています。
新基準の導入により、以下のような効果が期待されています。
ブランド価値の明確化と品質保証
誤表示や偽造品の流通抑制
消費者の識別しやすさと信頼性の向上
国際市場での信頼性と輸出促進
また、基準に適合しない製品については「ワールドウイスキー」など、別カテゴリとしての発展が促される可能性もあり、業界全体の透明性と多様性にもつながると期待されています。
国際比較:スコッチとバーボンの規制
ジャパニーズウイスキーの基準が整備されたことで、スコッチウイスキーやバーボンウイスキーといった世界的なウイスキー産地との共通点や違いがより明確になりました。
ここでは、それぞれの規制を比較しながら、ジャパニーズウイスキーがどのような位置付けにあるのかを整理します。
スコッチウイスキーの規制(Scotch Whisky Regulations 2009)
スコットランドで生産されるスコッチウイスキーは、英国政府によって定められた厳格な規制に従っています。これには、以下のような条件が含まれます。
生産地:スコットランド国内の蒸溜所で糖化・発酵・蒸留を行うこと。
原材料:水、大麦麦芽、および全粒の他の穀物(グレーンウイスキーの場合)。
蒸溜度数:94.8%未満。
熟成:スコットランド国内で、容量700リットル以下のオーク樽で3年以上熟成。
瓶詰め:40%以上のアルコール度数で瓶詰め。
添加物:プレーンカラメル(無香料)のみ使用可。
これらの規定は、スコッチウイスキーの品質と真正性を守るために制定されています。
バーボンウイスキーの規制(アメリカ連邦規則)
バーボンウイスキーはアメリカ国内で製造されるウイスキーで、連邦法により以下の要件を満たす必要があります。
生産地:アメリカ合衆国。
原材料:最低51%のトウモロコシを含む穀物。
蒸溜度数:80%未満。
熟成:新しい、内側を焦がしたオーク樽で熟成(熟成年数の下限はなし)。
瓶詰め:アルコール度数40%以上。
添加物:一切禁止(香味や色の調整を目的とした添加は不可)。
「ストレートバーボン」と名乗るためには、2年以上の熟成が求められます。
比較表:ウイスキーの規制要件
| 項目 | ジャパニーズウイスキー<br>(JSLMA自主基準) | スコッチウイスキー<br>(SWR 2009) | バーボンウイスキー<br>(米国連邦規則) |
|---|---|---|---|
| 原産地 | 日本 | スコットランド | アメリカ |
| 主原料 | 麦芽、およびその他の穀物(任意) | 大麦麦芽、他の全粒穀物(グレーンの場合) | 最低51%のトウモロコシ |
| 蒸溜地・度数 | 日本国内、95%未満 | スコットランド、94.8%未満 | アメリカ国内、80%未満 |
| 熟成 | 日本国内、容量700L以下の木製樽で3年以上 | スコットランド、容量700L以下のオーク樽で3年以上 | 新しい内側を焦がしたオーク樽で熟成(年数規定なし) |
| 瓶詰め | 日本国内、アルコール度数40%以上 | アルコール度数40%以上 | アルコール度数40%以上 |
| 着色 | プレーンカラメル(無香料)のみ使用可 | プレーンカラメル(無香料)のみ使用可 | 使用不可(添加物禁止) |
このように見ると、ジャパニーズウイスキーの新基準はスコッチと非常に似た構造を持っており、特に「熟成の最低年数」「瓶詰め度数」「着色料の制限」などで一致しています。一方、バーボンは原料・熟成・添加物の扱いなどで異なる基準が多く、その独自性が際立っていますね。

課題と今後の展望
ただし、こういった基準は現時点ではあくまで「自主基準」であり、法的拘束力はありません。
そのため、JSLMA非加盟の企業には適用されず、業界全体のルールとして確立するには限界もあります。
今後、法制化を進めることで、より強力な執行力と公平性が求められるでしょう。
一方、すべての工程を日本国内で行うという厳格な要件により、小規模な蒸溜所への負担が増すという懸念もあります。
とくに輸入原酒を使用したブレンドに依存していた一部事業者にとっては、転換が求められる厳しい基準です。
それでも、サントリーやニッカなど大手企業はこの基準を支持し、輸出製品はすでに準拠していると発表しています。
業界全体での自主的な取り組みが評価される中で、将来的な法整備への議論も活発になっています。